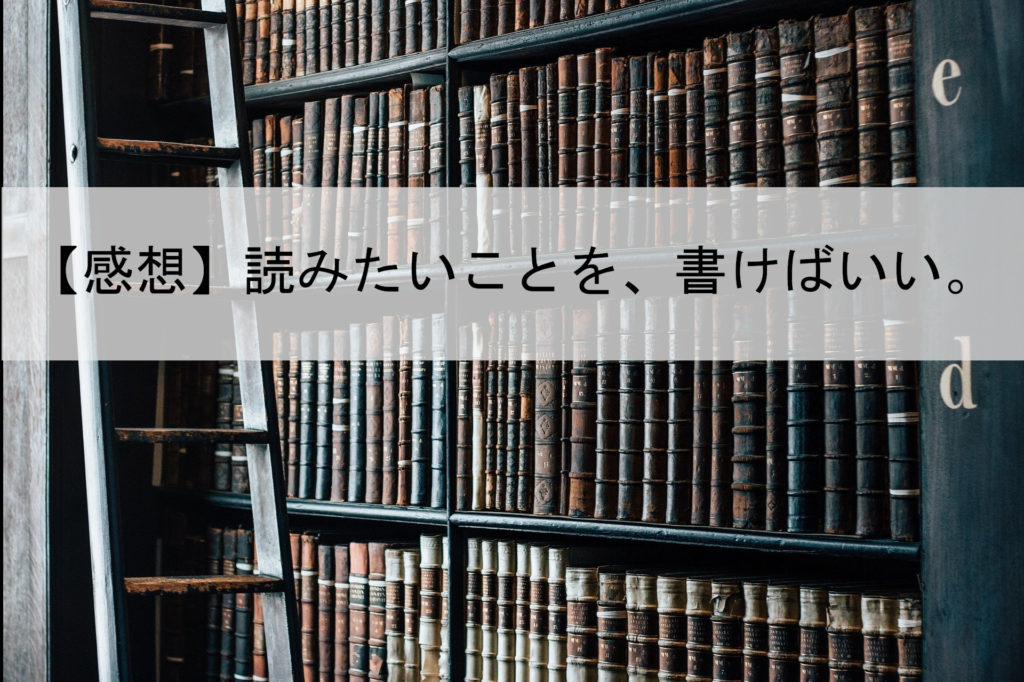はじめに
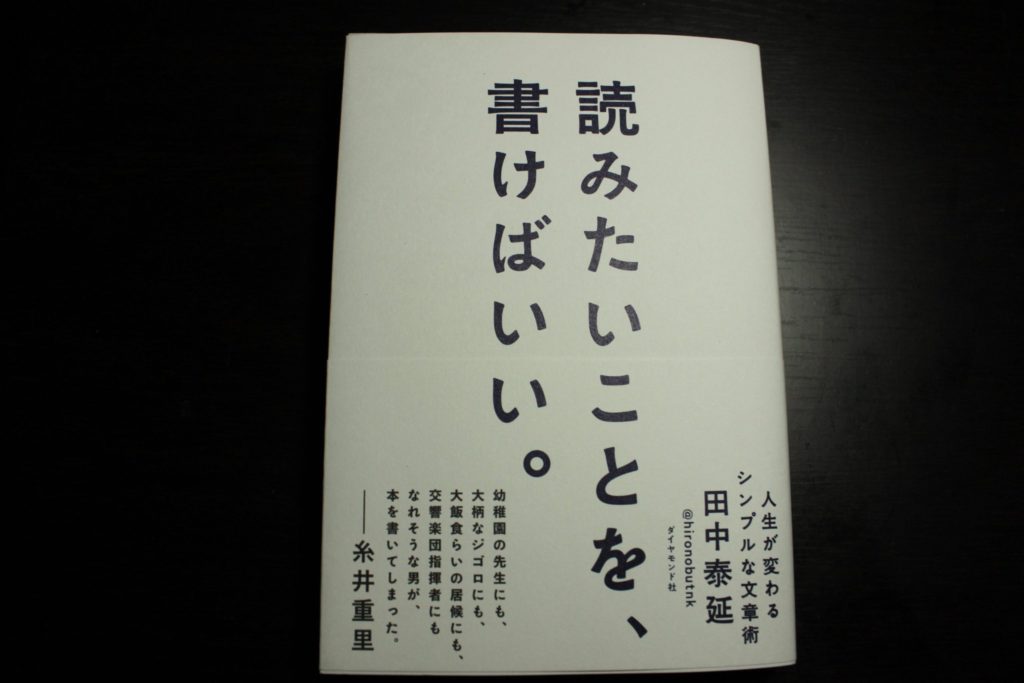
「読みたいことを、書けばいい。」
これは今回紹介する本のタイトルであり、概要となります。
本屋で文章術の本を探しているときに見つけました。
シンプルな表紙にひと目で探している本であることがわかりました。
文章術について述べている本ですが、具体的なノウハウはありません。ただ筆者自身が読みたいことが書かれています。
なぜそんなことがわかるのかと言うと、筆者自身が何度も言っているからです。
これだと説得力はないですね。正しくは読んでいて、筆者自身が楽しそうに書いているという気持ちが伝わってくるからです。
この記事でも少し見習って、自分に向けての備忘録として書いていきます。
著者情報
田中泰延
1969年大阪生まれ。
早稲田大学第二文学部卒
学生時代に6000冊の本を乱読。
1993年株式会社電通入社。
24年間コピーライタ・CMプランナーとして活動。
2016年に退職、「青年失業家」を自称しフリーランスとしてインターネット上でしっぴ活動を開始。
概要
「バズる記事を書きたい」
「ターゲットに刺さる文章を書きたい」
「自分の思いを読んでほしい」
そんな「技術」を学ぼうとする人は、出発点から間違っている。
もっとシンプルに、あなたが読みたいことを、あなたに向けて書けばいいのだ。
事実の中に、あなただけの発見を見出し、調べて、自分に向けて書く。
その結果、あなたは誰かとつながり、人生が変わる。
感想
自分がおもしろくもない文章を、他人が読んでおもしろいわけがない。だから、自分が読みたいものを書く。(p6)
文章を書くための大前提だと思います。かといって自分が面白ければいいのかと言われたら、もちろんそんな事はありません。
しかし、少なくても言えることは自分が読みたくないものは当然他人も読みたくないということです。
面白さはすべてとは限りませんが、少なくとも自分が読みたいものを書いていくことを意識していきたいと感じました。
深夜、暗い部屋で腰の痛みに耐えながらキーボードを打って、自分で書いたものに自分で少し笑う、それが「書く人」の生活である。(p107)
ここだけ読めば変な人だと思われそうですが、私もブログを書いてるときは同じ状況でした。違いがあるとすれば腰はまだ痛くないことくらいです。
だれも読まない。だれも読まないのである。なぜか。あなたは宇多田ヒカルではないからである。(p109)
これは本当です。よほどのメリットがない限り、一般人が書いたものを読むより、もっとほかの娯楽に時間を費やしたい人はたくさんいます。もちろん私も例外ではありません。
書いた内容よりも、誰が書いたかのほうがはるかに重要です。
ネタバレしますが、「あなたのローマ帝国1480年の歴史は宇多田ヒカルのロースカツ定食840円に完敗だ」というところで笑わせてもらいました。
「この人のギャグはすべっている」と批判してくる者もいる。しかし、すべるのがスキーだ。すべることもできない人間は、すべろうともしていないのだ。 (p114)
少々強引だが、言いたいことはわかります。口先だけよりも、行動している時点でスゴい。
いずれにせよ、評価の奴隷になった時点で、書くことがいやになってしまう。(p115)
評価は罠だと思います。良い評価を得られるために努力すると目的を見失います。
評価は自分では決められないので、それで一喜一憂するよりも、自分が出来ることに集中したほうが良い。
といっても評価を気にする気持ちはわかります。あまり意識しないようにしていきたいですね。
事象に出会ったとき、そのことについてしっかり調べて、愛と敬意の心象を抱けたならば、過程も含め、自分に向けて書けばいい。(p195)
文章の書き方についてこのことを意識すればだいぶ書きやすくなると感じました。調べた結果をまとめた上に、自分が感じたことを述べる。テンプレートとして使えそうです。
まとめ
「読みたいことを、書けばいい。」を読んだ感想について書きました。
最後の最後まで、筆者が書いてて楽しいという気持ちが伝わってきて、見習いたいと思いました。
実はこの本を読んだ直後、自分が読みたいものを試しに書いた記事はありますが、いろいろあって、あえてどの記事かはここでは書きません。
もしよかったら探してみてください。